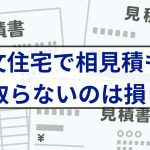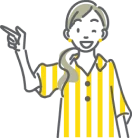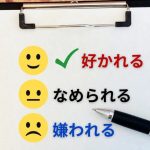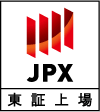注文住宅は在庫リスクがないため、値引きをする必要がないように思えますが、実際にはさまざまな理由で値引き交渉をする余地があります。
ここでは、注文住宅の値引きテクニックや値引きする際の注意点をわかりやすく解説します。
もくじ
注文住宅が値引きしにくい理由
注文住宅の建築には、数千万円単位の大量の資金が必要になることがほとんど。だからこそ、理想の家を形にしたいといった願望を持ちながらも、予算に限りがある人も多いはずです。
そこで、建築費用を抑えるために、値引き交渉ができないか?を考える人も多いことでしょう。しかし、注文住宅は値引きしにくいとされています。
では、なぜ注文住宅は値引きしにくいのでしょうか。その理由を詳しく解説します。
まだ建物(在庫)がないから、経年劣化という概念がない
注文住宅は契約を結んでから建材を発注したり、設備を用意したりして建築するため、建物(在庫)がありません。つまり、経年劣化という概念もありません。そのため、経年劣化を理由に価格交渉はできないのです。売れ残って価値が目減りするリスクがないため、「急いで売る必要」がないのです。
一方で、建売や分譲住宅のようにすでに建物(在庫)がある状態では、日がたつほど経年劣化していきます。
国税庁は耐用年数を定めており、日本の一般的な住宅構造である「木造」の耐用年数は22年です。つまり、新築で2,200万円の注文住宅を建築した場合、毎年100万円ずつ価値が下がり、22年後の価値は0円です。
【参考】国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
しかし、資産価値が0円になっても、木造住宅の耐久年数が22年というわけではありません。耐久年数は問題なしに住める年数であるのに対し、耐用年数はどのくらい不動産の価値が維持できるかを定めたものです。
なお、新築は住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められているとおり、過去に誰も住んだことのない、建築から1年未満の状態を指します。
建物(在庫)になって初めて経年劣化という概念が生まれるため、注文住宅が値引きしにくい理由となっています。
土地も経年劣化しないため値引きしにくい
注文住宅を建てる際に、土地を購入する人もいるでしょう。建物に加え土地の購入も必要となると、その費用を抑えたいと考えるのもうなずけます。
しかし、土地にも経年劣化という概念がないため、値引きしにくくなっています。
また、土地には消費税もかかりません。「劣化が生じない=消費しない」といった方程式が成り立つため、土地には消費税がかからないのです。
値引き交渉を成立しやすくするコツ
建物も土地も値引きがしにくいとなると、提示された金額で購入するしかないのでしょうか。
値引きはしにくいのは事実ですが、できないわけではありません。
ここでは、交渉を成立させやすくする以下の3つのテクニックを紹介します。
- 相見積もりを取る
- 契約直前のタイミングを狙う
- 決算時期や家が売れ残る時期を狙う
それぞれ詳しく解説します。
相見積もりを取る
値引き交渉を成立させやすくするには、相見積もりを取ることが大切。普段の生活でも、家電量販店などで「他店より高い場合には安くします」といった打ち出し、キャンペーンを見かけることがあると思います。
注文住宅を購入するときも同じこと。担当者は自分の会社で契約してほしいため、値引き交渉に応じてくれる可能性が高くなります。
ただし、会社も利益を出さなければならないため、むやみやたらに値引きはしないでしょう。具体的な値引き額を算出したいという理由で、他社の見積もりの提示を求められる場合があります。
その際、スムーズに交渉が進められるよう事前に他社の見積もりを用意しておき、「項目ごとの費用感」「構造や性能の違い」を把握しておくと説得力のある交渉ができます。
契約直前のタイミングを狙う
情報収集の時間から考えると実際の契約までにかかる期間は、少なくとも数カ月、長くて数年です。つまり、その期間のほとんどを、建築会社も一緒に過ごしていくことになります。
そのため、建築会社も契約が具体的になるタイミングでは、これまでの打ち合わせ時間や労力を水の泡にはしたくないという心理が働きます。だからこそ、その心理がもっとも高まる契約直前は値引き交渉がしやすくくなります。
値引き交渉する際には「あと〇〇万円値引きしてくれたら契約します!」と、具体的な金額条件を出して交渉しましょう。そうすると、希望金額と同等、もしくは近い金額を値引きしてくれる可能性が高まります。
決算時期や家が売れ残る時期を狙う
建築会社も営利企業であるため利益を出さなければならず、決算の時期は今期の業績が決まる重要なタイミング。
営業担当者としても今期の営業成績に関わる大切な時期のため、1件でも多くの契約を取りたいと考えます。
実際に会社をあげて決算セールを実施している場合もあり、値引きの交渉がしやすいタイミングとなります。
それぞれの会社の決算時期は、ホームページなどに記載されている場合が多いため、事前に確認しておきましょう。ただし、決算の時期までに契約まで進める必要があるため、契約までにかかる時間を逆算して計画的に動く必要があります。
また、家が売れ残る時期にも値引き交渉はしやすくなります。なぜなら、家が売れ残りやすい時期に契約してくれるお客様は、普段よりも貴重性が高いため、営業担当者も逃したくないと考えるからです。
一般的に、家が売れやすい時期は、新生活を始める人が多い2月から3月、次いで企業の異動や転勤などが多く、引越しを検討する人が増える9月から10月です。
比較的売れにくい時期は、年末年始と夏休みの期間です。
その他にも、建築会社の稼働状況によって「この時期に契約してほしい」というケースもあります。
スムーズに着工できるような時期、稼働に空きがある場合には価格を下げてくれることもあるようです。
値引き交渉するうえで起こりうるリスク
ここまで、値引き交渉のコツを解説してきましたが、値引きはよいことばかりではありません。値引き交渉をするうえで起こりうるリスクは以下のとおりです。
- 無理な値引き交渉は担当者からの不信を買う
- 住宅の品質が下がるおそれがある
それぞれ詳しく解説します。
無理な値引き交渉は担当者からの不信を買う
注文住宅の契約から引き渡しまでは早くて6カ月、遅ければ1年以上かかります。そのため、値引き交渉に応じた担当者とも長い付き合いになることでしょう。
値引き交渉だからといって強気に出たり、駆け引きをしすぎたりすると逆効果。担当者から不信を買ってしまえば、よいサービスを提供したいという気持ちをそぐ要因となるかもしれません。最悪の場合、値引きの有無に関わらず、契約を断られてしまうおそれもあります。
希望や予算を正直に伝え、「どこまでご相談できますか?」という姿勢が大切です。
担当者も「この人とは長く付き合えそう」と思えるお客様には前向きに対応したくなるもの。
親しき仲にも礼儀ありという言葉があるように、よい信頼関係を保っていくには、担当者への礼儀を忘れずに接することも大切です。
担当者と良好な関係が築ければ、値引きに対して積極的に動いてくれる可能性が高まるだけではなく、契約後のやり取りなどもスムーズに進められるでしょう。
住宅の品質が下がるおそれがある
相場から外れた無理な値引きを実施してしまうと、住宅の品質が下がるおそれがあります。なぜなら、値引きに対応するため人件費や材料費が削減されるかもしれないからです。
人件費を削減するために、評判のよいベテランの建築会社ではなく、経験の浅い建築会社に工事を依頼するかもしれません。また、納期を短縮して作業するケースも考えられます。加えて、材料費を削減するために、品質の悪い安い材料を使う場合もあるでしょう。
よいものを安く手に入れられるに越したことはありませんが、安かろう悪かろうという言葉があるように、安くしようとすれば品質が下がるおそれがあることも心得ておくことが大切です。
注文住宅の品質を下げない値引きの方法
注文住宅を建設するうえで費用がかかる部分を知り、譲れない重要なポイントを見極めておくと、住宅の品質を下げずに値引くことが可能です。
では、値引きしても注文住宅の品質を下げない方法とはどのような方法なのでしょうか。具体的な方法は、以下のとおりです。
- 外観や間取りを見直す
- 標準仕様を活かし、建材、仕様には柔軟に対応する
- 品質に定評のある建築会社を選ぶ
それぞれ詳しく解説します。
外観や間取りを見直す
住宅は平面より、「
外観のデザインは住宅の大切な要素にはなりますが、凹凸が多いほうが見栄えがよいわけではありません。シンプルなデザインでも、使う素材や色を工夫すれば、見栄えはよくなります。
また、間取りも品質を落とさずに値引ける部分です。たとえば、水まわりをひとつにまとめたり、子ども部屋を小さくしたりする方法などがあります。
水まわりは、ひとつにまとめることで配管工事の費用を抑えられます。さらには、家事がしやすくなったり、メンテナンスがしやすくなったりといったメリットもあるため、おすすめです。
子ども部屋は、家族同士のコミュニケーションを増やすために、あえて小さくするといった選択肢もあります。
子どもが独立して家を出ていくと空き部屋になる可能性もあるため、将来のことも考えて間取りを見直してもよいでしょう。
標準仕様を活かし、建材、仕様には柔軟に対応する
住宅会社が提示する標準仕様には、コストと性能のバランスが取れた設備や建材が揃っています。必要以上にグレードアップをせず、標準の中で工夫することで費用を抑えることが可能です。
また、使用する建材や設備機器も、メーカーからの仕入れ値に差があり、商品を変えることでコストを抑えられることがあります。この差額を「値引き」として反映してもらうことも可能です。
品質に定評のある建築会社を選ぶ
住宅をカタチにしてくれる建築会社選びは、もっとも大切。
建築会社は大きく、ハウスメーカー・工務店・設計事務所の3種類に分けられ、それぞれ品質にも特徴があります。
ハウスメーカーは全国に拠点をもっている大手のことが多いため、大量生産を実現しなければなりません。実現するために設計や施工方法を会社として標準化し、建築資材も工場でまとめて加工するなどのコストダウンを行うことが一般的なため、一定の品質が保たれます。
また、資金力もあるため、品質の向上に費用をかけているハウスメーカーも多数あります。
工務店や設計事務所は大量生産というよりは、お客様ごとの要望に合わせて建築することが多いです。事業規模や得意としているデザイン、工法も異なり、建築会社の腕前にもよるため、品質にバラつきが生じることもあります。
ハウスメーカーは広告費用をかけているため、比較的情報を収集しやすいですが、工務店や設計事務所は広告費をかけずに、地域に密着して事業を営んでいる場合も多いでしょう。
情報を収集する際はインターネットや雑誌を活用したり、不動産会社に協力してもらったりしながら、品質に定評のある建築会社を選びましょう。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)