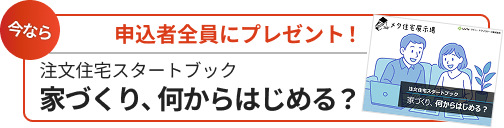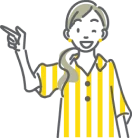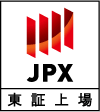注文住宅における冬の快適さは「暖房器具の性能」よりも「断熱性能の高さ」で決まります。
断熱性能の高い家はエネルギー効率が非常に高く、暖房器具の省エネ運転でも快適な温度を維持しやすいためです。温度ムラも起きにくいので、一年を通して心地よく過ごせます。
ただし、断熱性能の高い家を建てる際は、いくつか注意点があります。暖かい家づくりのために、押さえておくべきポイントを確認していきましょう。
もくじ
暖房を付けていても家の中が暖かくならない3つの原因
暖房しても室内が暖まりにくい家には、主に3つの原因があります。
- ①窓付近で発生するコールドドラフト
- ②断熱性能が不十分
- ③気密性の低下による隙間風
上記の原因について、そのメカニズムと影響を詳しく見ていきます。
①窓付近で発生するコールドドラフト
コールドドラフトとは、外の冷たい空気によって窓やサッシが冷やされ、その冷たさが室内側に伝わることで起こる現象です。窓付近の冷やされた空気は、室内の暖かい空気よりも重いため、下降気流となって床へ流れ落ちます。
室内の上部と下部で5度以上の温度差が生じることもあり、頭部は暖かいのに足元が冷たいという不快な温度ムラが発生します。単板ガラスやアルミサッシといった断熱性の低い窓では、コールドドラフトをはっきりと感じられることが多いです。
②断熱性能が不十分
断熱性能とは、家の中の熱を外に逃がさず、外の冷気や暑さを伝えにくくする力のことです。
壁だけでなく、屋根や床、基礎まで隙間なく断熱材が入っている家は、発泡スチロールの箱のように外気の影響を受けにくく、室内の温度を保ちやすくなります。また、窓や窓枠の断熱性能もとても重要です。窓は家の中で最も熱が出入りしやすい場所のひとつなので、樹脂サッシや複層ガラスなどを使うことで、より快適で暖かい住まいに近づけます。
少ない暖房でも冬は暖かく、夏は冷房効率が良くて涼しく過ごせるのが特徴です。部屋ごとの温度差も小さいため、一年を通して快適に暮らせます。
しかし、断熱材が次のような状態になっていると、家全体で熱を十分に保てなくなる可能性があります。
- 断熱材の厚みが足りない
- 工事が丁寧でなく、すき間ができてしまう
- 断熱材が家全体をしっかり覆っていない
- 窓のまわりの断熱が不十分
- 柱や梁(はり)との境目に断熱材が行き届いていない
上記のような不備があると、暖房で室内を暖めても熱が逃げてしまい、光熱費がかさむ原因になります。そのため、断熱材は厚みや施工精度をしっかり確保することが大切です。
③気密性の低下による隙間風
暖かい家を建てるなら、気密性も欠かせない要素です。
気密性が低いと、暖房で温めた空気がすき間から外に逃げ、同時に冷たい外気が室内に入り込んでしまいます。その結果、いくら暖房を強くしても室温は上がりにくくなってしまいます。
また、気密性が低い住宅では、計画的な換気ができないという問題も生じます。24時間換気システムが正常に機能せず、想定外の場所から外気が侵入することで、フィルターを通さない汚れた空気や花粉などが室内に入り込む可能性があります。
気密性が低い家はすき間が多いため、室内の暖かい空気が壁の中に入り込んでしまいます。
壁の中は外気に触れて冷たくなっている部分があるので、そこに暖かい空気が触れると水滴(結露)が発生します。
この結露が続くと、柱や断熱材が傷んだり、カビが発生したりする原因になります。少し専門的になりますが、気密性はC値(相当隙間面積)で表され、数値が小さいほど隙間が少ない高気密住宅となります。
一般的に、C値1.0平方センチメートル毎平方メートル以下であれば高気密住宅とされていますが、より高い性能を求める場合は0.5以下を目標とすることが望ましいです。
暖かい家づくりに欠かせない5つのポイント
快適で暖かい家にするためには、いくつかのポイントを組み合わせて考えることが大切です。ひとつの工夫だけでは十分な効果が得られないので、次の5つの視点からバランスよく計画を立てましょう。
- ①断熱性を高めて熱を逃さず冷気も入れない
- ②熱交換型換気で新鮮な空気と暖かさを両立
- ③適切な暖房設備で効率的に家を暖める
- ④間取りを工夫して暖かい空気を1階に留める
- ⑤補助金の活用でコストを抑える
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
①断熱性を高めて熱を逃さず冷気も入れない
家の断熱性能を高めれば、少ないエネルギーで家の中を暖かく保つことができ、光熱費の節約にもつながります。
断熱性能を良くするためには、次のような工夫が大切です。
- 断熱材の種類選び(グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンフォームなど)
- 家全体を途切れなく覆うこと(基礎から屋根まで断熱層をつなげる)
- 熱が逃げやすい部分への対策(コンセントの裏や配管のまわりなど)
- 窓やドアの断熱性を高めること
断熱は、室内の熱を外に逃がさず、外の冷たい空気を入れないための基本です。特に重要なのは、家を隙間なく断熱材で包むことです。どこかに切れ目があると、そこから熱が逃げてしまい、性能が大きく下がります。コンセントや配管まわりなど、細かい部分まできちんと断熱することが必要です。
また、窓やドアの断熱も忘れてはいけません。これらは熱の出入りが一番多い場所だからです。樹脂サッシとトリプルガラスの組み合わせなら、非常に高い断熱性能が得られ、窓の近くでも冷えを感じにくくなります。
なお、断熱材には多くの種類があり、熱を通しにくさ、耐久性、施工のしやすさ、費用など特徴が異なるので、建てる地域の気候や予算に合わせて選ぶことが大切です。
②熱交換型換気で新鮮な空気と暖かさを両立
新築住宅にはすべて24時間換気システムの設置が義務付けられています。
これは、シックハウス症候群などの健康被害を防ぎ、室内の空気を常に新鮮に保つためです。特に高断熱・高気密の家では、計画的に空気を入れ替えるためにこのシステムが欠かせません。
しかし、ただ入れ替えるだけだと、せっかく暖めた室内の空気が排出されるため、エネルギーの無駄になってしまいます。
この問題を解決するのが「第一種熱交換換気システム」です。これは、外に出す空気の熱を回収して、新しく取り入れる外気に移す仕組みで、換気による熱の損失を大幅に減らしてくれます。
例えば、熱交換効率が90%以上の高性能タイプなら、外気温が0度でも取り込む空気を18度前後まで暖められます。そのため、換気口から冷たい風が入ってくる不快感がなく、常に新鮮な空気を取り入れながら快適な室温を保てます。
「第一種熱交換換気システム」の効果を最大限に得るには、家自体の気密性がきちんと確保されていることが大前提です。すき間が多い家では空気が予定外のところから出入りしてしまい、熱交換の効果が下がってしまうからです。つまり「気密」と「換気」はセットで考える必要があります。
③適切な暖房設備で効率的に家を暖める
高断熱・高気密の家は、熱が逃げにくいため、暖房機器の省エネ運転でもしっかりと暖められます。
しかし、家の性能や間取りに合った機器を選ばないと、暖まりにくかったり余計なコストがかかったりします。
暖房設備を選ぶときは、家の性能や地域の気候に合わせた「暖房負荷計算」に基づいて決めることが大切です。大きすぎるとコストとエネルギーが無駄になり、小さすぎると十分に暖まらないため、専門家に相談して最適な計画を立てましょう。例えば、暖房設備には次のような選択肢があります。
| 暖房設備 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| エアコン | ヒートポンプ技術を使った省エネ暖房 | 省エネ性能が高い・高断熱住宅なら少ない台数で全体を暖められる | 台数・容量は専門家の計算が必要・条件次第では部屋ごとに追加設置が必要 |
| 全館空調システム | 1台で家全体を均一に暖める仕組み | 家中の温度差が少なく快適・長期的にはコストが抑えられることもある | 初期費用が高い・導入時に十分な計画が必要 |
| 床暖房 | 足元からじんわり暖める輻射暖房 | 足元が暖かく快適・ヒートショックの防止に役立つ | 設置費用がかかる・全体暖房には向かない場合もある |
暖房設備は組み合わせも大事なので、家の断熱性や地域の気候を踏まえて、専門家に相談しながら最適な方式を決めることが大切です。
④間取りを工夫して暖かい空気を1階に留める
家の間取りは、暖房の効きやすさに大きく関わります。
暖かい空気は軽くて上にのぼる性質があるため、この特徴を考えた間取りにすると、効率よく家全体を暖められます。
例えば、吹き抜けやリビング階段は開放的でおしゃれですが、暖かい空気が2階へ逃げやすいのが難点です。対策としては、シーリングファンで空気を循環させたり、階段にロールスクリーンや引き戸をつけて熱が逃げないようにする方法があります。
また、各部屋のドアの下に小さなすき間(アンダーカット)を設けると、暖かい空気が家全体に回りやすくなります。ただし、換気の流れを妨げないよう注意が必要です。脱衣所やトイレなど普段はあまり意識しない空間も、冷えすぎないように工夫が必要です。全館空調の吹き出し口をつけたり、小型の暖房器具を置いたりすることで、家全体の温度差を小さくできます。
さらに、太陽の熱を活かす工夫も大切です。南側に大きな窓を設けると、冬の日中に太陽熱を取り込み、暖房の助けになります。ただし夜は熱が逃げやすいため、高性能な窓を選ぶことが前提です。
⑤補助金の活用でコストを抑える
高断熱・高気密住宅の建築には、通常の住宅よりも初期投資が必要となりますが、国や地方自治体が提供する様々な補助金制度を活用することで、経済的な負担を大幅に軽減することができます。
活用可能な主要な補助金・優遇制度は以下の通りです。(2025年9月時点)
| 制度名 | 補助金額例 | 対象・条件の目安 |
|---|---|---|
| ZEH支援事業 |
|
高い省エネ性能を持つ住宅 |
| 子育てグリーン住宅支援 | 最大 160万円 | GX志向型住宅など、一定の省エネ基準を満たす住宅 |
| 長期優良住宅 / 認定低炭素住宅 | 税制優遇(住宅ローン減税・固定資産税減免など) | 認定を受けることが条件 |
予算枠に達すると早期に終了する制度もあるため、計画段階から情報収集を行い、建築会社と連携して適切な時期に申請を行う必要があります。
建築前に確認!暖かい家の見分け方
住宅の温熱性能は、完成後に改善することが困難であるため、建築前の段階で十分な確認を行うことが極めて重要です。
カタログ上の数値だけでなく、実際の性能や住み心地を様々な角度から検証することで、本当に暖かい家を建てることができます。ここでは、建築前に実施すべき3つの確認方法について詳しく解説します。
住宅性能表示制度の活用
住宅性能表示制度とは、国に認められた第三者の機関が、家の性能を客観的にチェックして等級(数字)で表してくれる制度です。
この制度を使えば、専門的な知識がなくても、家の断熱性や省エネ性をわかりやすく確認できます。断熱性は「断熱等性能等級」という指標で表され、1から7まであり、数字が大きいほど性能が高いことを示します。現在の最低基準は、等級4ですが、快適に過ごすためには最低でも等級5(ZEH基準に相当)以上が望ましいとされています。
建設評価まで取れば「設計通りの性能がちゃんと実現されている」と第三者が保証してくれるので安心です。
なお、この制度には気密性を直接評価する項目はありませんが、C値(すき間の少なさを示す数値)の測定を建築会社にお願いすることができます。目標値を設定して測定してもらえば、気密性能もしっかり確認できます。
口コミの確認
実際にその建築会社で家を建てた人の体験談は、カタログやモデルハウスでは分からない貴重な情報源となります。
インターネット上の口コミサイトやSNSを活用することで、多様な意見を収集できます。
効果的な口コミ情報の収集方法は以下の通りです。
- 第三者サイトの両方から情報収集
- SNSでのハッシュタグ検索によるリアルタイム情報の入手
- アフターサービスに関する評判の確認
ただし、SNSや掲示板に書かれている口コミは、必ずしも信頼できるとは限りません。あくまで参考程度にとどめ、最終的には自分の目で見て体験して確かめることが大切です。
宿泊体験やOB訪問
ハウスメーカーの中には、モデルハウスに泊まれる宿泊体験や、実際に家を建てた人の住まいを訪ねるOB訪問を実施しているところがあります。
宿泊体験では、その家が本当に暖かいかどうかを自分の体で確かめられるのが大きなメリットです。
昼間だけの見学では気づきにくい夜や朝の寒さ、暖房を消したあとの温度の下がり方、部屋ごとの温度差などを体感できます。さらに、窓の近くで冷気を感じるかどうかを確認したり、実際の光熱費がどのくらいかかるのかを知ったりすることもできます。
また、OB訪問では、実際に暮らしている人から住み心地や光熱費、アフターサービスの対応などを直接聞けます。モデルハウスでは分からないリアルな生活の様子を知ることができる貴重な機会です。宿泊体験やOB訪問を利用することで、家がどれだけ暖かく快適かを具体的にイメージでき、理想の住まいづくりの参考になります。
土地探しから資金計画まで!暖かい家を建てるトータルサポート
メタ住宅展示場を使えば、自宅にいながら複数の建築会社からプランや費用の提案を無料で受け取れます。
大手から地元の工務店まで参加しており、断熱性能や費用を比較しやすいのが特徴です。土地選びのアドバイスや補助金情報、将来の光熱費まで含めた資金計画を提案してもらえるので安心です。断熱・気密・換気・暖房・間取りといった要素を総合的に整えて、快適な暖かい家づくりを実現しましょう。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)