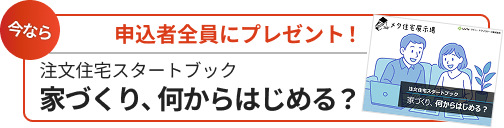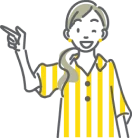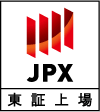日本の夏は、ここ数年で観測史上の「最暑記録」を次々と更新しています。
特に2025年の夏(6〜8月)は、過去2年の記録を大きく塗り替える勢いとなっており、全国各地で平均気温が過去最高レベルに達すると見込まれています。また、気温が高くなれば、室内の温度も上がりやすくなります。エアコンは、室内を冷やそうとしてより多くの電力を使うようになり、その結果、電気代が増えて家計を直撃します。
こうした状況から、注文住宅を建てる際は、夏でも涼しく快適に過ごせる家づくりが欠かせません。
では、注文住宅を建てる際、厳しい夏の暑さを光熱費を抑えながらも涼しく過ごすには、どのような方法があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
もくじ
家の中が涼しくならない3つの原因
夏場にエアコンをかけても家の中が涼しくなりにくい場合、主に3つの原因が考えられえます。
- ①窓から侵入する日射と輻射熱
- ②屋根・小屋裏・外壁の蓄熱
- ③気密性が低く”すき間”から外気が出入りする
特に影響の大きい3つの原因について、そのメカニズムと影響を詳しく見ていきましょう。
①窓から侵入する日射と輻射熱
YKK AP株式会社によれば、夏場に住宅内部へ流入する熱の約70%が窓などの開口部から入ってくるとされており、窓は外気の熱を最も通しやすい部位といえます。
これは、対流・ふく射・伝導といった熱の移動のうち、特に窓がその大半を占めてしまうためです。冬には室内の暖房熱の約50%が窓から流出するとされ、省エネルギーの観点からもサッシや窓の断熱性向上が極めて重要になります。
出典:YKK AP「開口部の断熱性能」
特に問題となるのが西日です。
午後の太陽は高度が低いため、室内の奥深くまで日射が届きます。この直射日光により、床や壁、家具などの表面温度が急激に上昇し、それらが熱を蓄えて輻射熱を放出し続けます。
一般的な単板ガラスの窓では、日射熱取得率が0.86~0.88程度とされます。これは、外から入ってくる太陽光の熱のうち約86~88%がそのまま室内に透過してしまうことを意味します。
つまり、ほとんどの熱を遮れずに室内に取り込んでしまうため、夏場の室温上昇を大きく招く要因となります。複層ガラスであっても、遮熱性能が低ければこの透過を十分に抑えることはできず、効果は限定的です。
さらに厄介なのは、窓枠やサッシ自体も熱を帯びることです。特にアルミサッシは熱伝導率が高く、外気温が35℃を超えるような真夏日には、サッシ自体が熱源となって室内に熱を伝えてしまいます。
このような状況では、エアコンで室内の空気を冷やしても、窓周辺から絶えず熱が供給され続けるため、冷房効率が著しく低下します。「部屋の中央は涼しいのに、窓際だけ暑い」という現象は、まさにこの輻射熱が原因なのです。
②屋根・小屋裏・外壁の蓄熱

建物の屋根や外壁が蓄える熱も、室温の上昇に大きな影響を与えます。
真夏の直射日光を受けた屋根の表面温度は、60℃を超えることも珍しくありません。
屋根の蓄熱で問題となるのが小屋裏空間です。天井裏にあたるこの空間は、屋根からの熱が直接伝わるため、外気温37℃時に小屋裏が60℃まで上昇した実測例があります。断熱材が不十分な場合、この熱が天井を通じて室内へじわじわと伝わってきます。
出典:天井裏の温度について|有限会社 木の香の家-木精空間-
外壁についても同様で、コンクリート造や濃い色の外壁材は、日中に大量の熱を蓄積します。この蓄熱された熱は、夜間になっても放出され続けるため、室温がなかなか下がらない原因となります。この現象は「熱容量」という物理的性質によるものです。
重量のある建材ほど熱を蓄えやすく、一度温まると冷めにくい特性があります。瓦屋根やコンクリート外壁などは、この熱容量が大きいため、日没後も長時間にわたって放熱を続けます。結果として、エアコンで室内を冷やしても、天井や壁から絶えず熱が供給されるため、冷房負荷が増大し、電気代の増加にもつながってしまうのです。
③気密性が低く”すき間”から外気が出入りする
建物には、施工上どうしても生じる微細な隙間が存在します。窓枠と壁の取り合い部分、コンセントボックス周り、配管貫通部など、様々な箇所に隙間が生じる可能性があります。気密性能を表す指標として「C値(相当隙間面積)」があります。これは、建物全体の隙間面積を床面積で割った値で、数値が小さいほど気密性が高いことを示します。
高気密住宅では1.0㎠/㎡以下が目安とされていますが、一般的な住宅では5.0㎠/㎡を超えることも少なくありません。気密性が低い住宅では、エアコンで冷やした室内の空気が隙間から漏れ出し、代わりに高温の外気が侵入してきます。これでは、穴の開いたバケツに水を注ぐようなもので、いくら冷房しても効果が得られません。
また、計画換気システムを導入していても、建物に多くの隙間があると、想定した換気経路とは異なる場所から空気が出入りしてしまいます。これにより、部屋ごとの温度差が生じやすくなり、「1階は涼しいが2階は暑い」「廊下だけ暑い」といった温度ムラが発生してしまうのです。
夏でも涼しく快適な注文住宅に欠かせない5つのポイント
夏の暑さの原因を理解したところで、次は具体的な対策について見ていきましょう。
涼しい家づくりには、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。単一の対策だけでは限界があるため、総合的な視点で計画を立てる必要があります。以下に紹介する5つのポイントは、それぞれが相互に作用し合い、快適な住環境を実現するための基盤となります。
設計段階から施工、そして住み始めてからの運用まで、各段階で意識すべき重要な要素を詳しく解説していきます。
①まずは直射日光を「外から」さえぎる
日射遮蔽は、夏の涼しさを実現する上で最も基本的かつ効果的な対策です。重要なのは、日射を室内に入れる前に遮ることです。
- 外付けブラインド(日射熱約80%カット、高額だが効果大)
- 日除けシェード(手軽で安価、5~7万円程度)
- 庇(ひさし)の設置(恒久的でメンテナンスフリー)
- 方角別の対策(南面は庇、東西面は縦ルーバー)
- 落葉樹の植栽(自然の日陰、季節対応)
外付けブラインドは、窓の外側に設置することで、日射熱を約80%カットできるとされています。
これに対し、室内ブラインドでは約50%程度の遮蔽率にとどまります。ただし、設置費用は1窓あたり数十万円と高額で、強風時には巻き上げる必要があるなどの運用上の制約もあります。
出典:外付けブラインド 「ヴァレーマ」|東京ガーデニングスタイル
より手軽な選択肢として、日除けシェードがあります。LIXILの「スタイルシェード」などは中窓で5~7万円前後(工事込み目安)で設置可能で、必要な時期だけ使用できる利便性があります。ただし、耐久性の面では劣り、数年ごとの交換が必要になることもあります。
出典:日よけ・オーニング|LIXIL
また、建築的な対策として、庇(ひさし)の設置も効果的です。適切な長さの庇は、夏の高い太陽を遮りながら、冬の低い太陽光は取り込むことができます。一度設置すれば恒久的に機能し、メンテナンスもほとんど不要です。方角別の対策も重要です。
南面は庇が効果的ですが、東西面の低い角度から差し込む日射には、縦型のルーバーや格子が有効です。特に西日対策は重点的に行う必要があり、複数の手法を組み合わせることが推奨されます。自然の力を活用する方法として、落葉樹の植栽も検討に値します。夏は葉が茂って日陰を作り、冬は葉が落ちて陽の光を室内に取り込めるため、季節に応じた自然な調整が可能です。
②間取りを工夫して熱をためない・逃がす
住宅の間取り設計は、夏の涼しさに大きく影響します。熱をためない、効率的に逃がすという視点で計画することが重要です。
- 風の通り道の確保(入口と出口を対角線上に配置)
- 風の入口と出口のサイズ調整(ベンチュリー効果の活用)
- 吹き抜けや階段空間の活用(可動式仕切りで調整)
- 西向きの部屋配置の工夫(非居室をバッファゾーンに)
まず基本となるのが、風の通り道の確保です。
単に窓を設けるだけでなく、風の入口と出口を対角線上に配置することで、効果的な通風が可能になります。
南北、東西など、2方向以上に開口部を設けることが理想的です。
風の入口となる窓を小さめに、出口となる窓を大きめにすることで、ベンチュリー効果により風速が増し、より効果的な換気が実現できます。
ただし、この設計には地域の卓越風向を考慮する必要があります。吹き抜けや階段空間の扱いも重要です。温かい空気は上昇する性質があるため、これらの縦方向の空間は熱の逃げ道として機能します。
しかし、冷房時には冷気も逃げてしまうため、必要に応じて仕切れる工夫が必要です。例えば、吹き抜け部分にロールスクリーンや可動式の天幕を設置することで、状況に応じて空間を区切ることができます。日中は閉じて冷房効率を高め、夜間は開放して自然換気を促すといった使い分けが可能になります。
西向きの部屋配置にも注意が必要です。寝室や子供部屋など、長時間過ごす部屋を西側に配置すると、午後から夕方にかけて室温が上昇し、就寝時まで暑さが残ってしまいます。西側には、収納室や水回りなどの非居室を配置することで、バッファゾーンとして機能させることができます。
③通気を確保して、こもった熱を外へ逃がす
建物内部にこもった熱を効率的に排出するためには、計画的な通気設計が不可欠です。
高断熱・高気密化が進む現代の住宅では、意図的に通気経路を設けないと、熱が滞留してしまいます。小屋裏換気は特に重要です。屋根裏空間は夏場に最も高温になる場所であり、ここに溜まった熱気を排出することで、天井からの熱の侵入を大幅に軽減できます。
効果的な小屋裏換気には、軒先から外気を取り入れ、棟から排出する自然換気方式が一般的です。温度差による浮力と風圧を利用して、継続的な空気の流れを作り出します。さらに効果を高めるために、温度センサー付きの換気扇を設置する方法もあります。小屋裏温度が一定以上になると自動的に作動し、強制的に熱気を排出します。
外壁通気工法も、現代の住宅では標準的な仕様となっています。外装材と防水層の間に通気層を設けることで、壁内部の熱や湿気を排出します。通気層は下部と上部に開口部を設け、煙突効果により自然に空気が流れる構造とします。これにより、壁内部の温度上昇を抑制し、同時に内部結露のリスクも軽減できます。
重要なのは、これらの通気経路が途中で遮断されないことです。設計段階で通気ルートを明確にし、施工時にも確実に連続性を確保する必要があります。断熱材の充填や配管・配線工事の際に、通気経路を塞がないよう注意が必要です。
④熱交換換気で冷えた空気を逃がさずに入れ替え
現代の高気密住宅では、建築基準法により24時間換気システムの設置が義務付けられています。しかし、通常の換気では、せっかく冷やした室内の空気をそのまま排出してしまうため、エネルギーロスが生じます。
熱交換型換気システムは、この問題を解決する画期的な設備です。排気する空気から熱(冷熱)を回収し、給気する新鮮な外気に移すことで、室内の温度を保ちながら換気を行います。
例えば、外気温が35℃の真夏日でも、熱交換効率が70%のシステムであれば、室温25℃の場合、給気温度を28℃程度まで下げることができます。これにより、冷房負荷を大幅に軽減できます。
出典:換気の基礎知識|三菱電機
第一種換気システム(機械給気・機械排気)と組み合わせることで、家全体の空気の流れを計画的にコントロールできます。各部屋への給気量と排気量を調整することで、温度ムラの少ない快適な環境を実現できます。熱交換換気システムには、顕熱交換型と全熱交換型があります。全熱交換型は温度だけでなく湿度も交換するため、夏の高湿度対策にも効果的です。
ただし、初期費用は通常の換気システムより高額で、一般的な住宅で数十万円の追加コストがかかります。また、フィルターの定期的な清掃や、熱交換素子の交換などのメンテナンスも必要です。
それでも、長期的な省エネ効果と快適性の向上を考えれば、十分に投資価値のある設備といえるでしょう。
⑤補助金の活用でコストを抑える
高性能な住宅の建築には相応のコストがかかりますが、国や自治体の補助金制度を活用することで、負担を軽減できます。
- ZEH支援事業(2025年度:ZEH 55万円、ZEH+ 90万円)
- 長期優良住宅認定制度(税制優遇あり)
- 地域独自の補助制度(自治体による)
- 申請時の注意点とスケジュール管理
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業は、代表的な補助制度の一つです。一定の断熱性能と省エネ設備を備えた住宅に対し、2025年度はZEHで55万円、ZEH+で90万円の補助枠が案内されています。
長期優良住宅認定制度も見逃せません。認定を受けることで、住宅ローン控除の優遇や固定資産税の減額など、税制面でのメリットを受けることができます。
地域独自の補助制度も確認しましょう。自治体によっては、太陽光パネルの設置や高性能窓への改修に対する助成金を用意している場合があります。重要なのは、これらの補助金には申請期限や要件があることです。着工前に申請が必要な制度も多いため、計画段階から建築会社と情報を共有し、スケジュールを調整する必要があります。
各制度の詳細は年度ごとに更新されるため、必ず最新の公募要領を確認し、建築会社と早めに相談することをお勧めします。補助金の要件を満たすために必要な性能向上のコストと、受給できる補助金額を比較し、最適なバランスを見つけることが大切です。複数の制度を組み合わせることで、より大きな支援を受けられる場合もあります。
建築会社の中には、補助金申請のサポートを行っているところもあります。経験豊富な会社であれば、申請書類の作成から提出まで、スムーズに進めることができるでしょう。
建築前に確認!涼しい家の見分け方
住宅の契約前に、本当に涼しい家になるのか見極めることは極めて重要です。
カタログやモデルハウスだけでは実際の性能は分かりにくいため、客観的な指標と実体験を組み合わせて判断する必要があります。性能の数値化、実際の居住者の声、そして自分自身の体感という3つの視点から確認することで、後悔のない家づくりが可能になります。以下では、それぞれの確認方法について具体的に解説していきます。
住宅性能表示制度の活用
住宅の性能を客観的に評価する方法として、住宅性能表示制度があります。
これは第三者機関が住宅の性能を評価し、等級で表示する制度です。断熱等性能等級は、住宅の断熱性能を1から7の等級で評価します。2022年に等級6と7が新設され、より高い性能の評価が可能になりました。等級7は現在の最高等級で、HEAT20のG2からG3レベルに相当する非常に高い性能を示します。
2025年4月からは、新築住宅で省エネ基準適合が義務化されましたが、これは最低基準に過ぎません。真に涼しい家を目指すなら、等級5以上、できれば等級6や7を目標とすべきです。
出典:国土交通省「建築物省エネ法改正」
UA値(外皮平均熱貫流率)は、建物全体の断熱性能を示す重要な指標です。数値が小さいほど断熱性能が高く、地域区分により基準値が設定されています。夏の涼しさに特に関係するのが、ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)です。この値が小さいほど、夏の日射熱の侵入を防ぐ性能が高いことを示します。
設計段階で設計住宅性能評価を取得し、完成後に建設住宅性能評価を取得することで、図面通りの性能が実現されているか確認できます。これらの評価書は、将来の売却時にも性能の証明として有利に働くため、取得しておく価値は十分にあります。
口コミの確認
実際にその住宅会社で建てた人の声は、貴重な情報源です。
インターネット上の施主ブログやSNS、住宅系の掲示板などで、リアルな体験談を収集しましょう。
- 夏の涼しさに関する具体的な感想
- 電気代の実数値情報
- 西日対策や通風の工夫についての言及
- 地域性を考慮した事例の選定
- アフターサービスの評判
特に注目すべきは、「夏の涼しさ」に関する具体的な感想です。「真夏でもエアコン1台で家全体が涼しい」「2階の寝室でも快適に眠れる」といったポジティブな声が複数あれば、信頼性が高いと判断できます。電気代に関する情報も重要です。
「オール電化で真夏の電気代が○○円」といった具体的な数値は、その住宅の省エネ性能を推測する材料となります。西日対策や通風の工夫についての言及も参考になります。「西側の部屋も暑くない」「風通しが良くて気持ちいい」といった声は、設計の良さを示しています。
地域性も考慮しましょう。同じ地域、似たような立地条件の事例を優先的に参考にすることで、より現実的な判断ができます。
アフターサービスの評判も確認すべきポイントです。引き渡し後の不具合対応や、性能調整のサポート体制が整っている会社は信頼できます。
宿泊体験やOB訪問で実際の涼しさを体感
百聞は一見に如かず、実際に体感することが最も確実な確認方法です。
多くの住宅会社が、モデルハウスでの宿泊体験やOB施主宅の見学会を実施しています。
宿泊体験では、できれば真夏の暑い日や梅雨時の蒸し暑い日を選びましょう。エアコンの設定温度と実際の体感温度の関係、各部屋の温度差、夜間の快適性などを確認できます。特に重要なのは、2階や最上階の寝室の温度です。就寝時に快適な温度が保てるか、朝まで涼しさが続くかを体感しましょう。
温湿度計を持参して、各部屋の温度と湿度を測定することをお勧めします。数値化することで、より客観的な判断が可能になります。OB訪問では、実際の生活の中での使い勝手を確認できます。エアコンの使用状況、日除けの運用方法、季節ごとの快適性など、住んでいる人だからこそ分かる情報を得られます。
「猛暑日でもエアコンは何時間くらい使いますか」「電気代はどの程度ですか」といった具体的な質問をしてみましょう。多くの施主は、自分の家の快適性について喜んで話してくれるはずです。
西日が当たる部屋や、北側の部屋など、条件の悪い場所の快適性も確認しましょう。どの部屋でも快適に過ごせるかは、住宅全体の性能を判断する重要な指標となります。
夏でも涼しい注文住宅を建てるために「家づくりプラン」がトータルサポート
涼しい家づくりを成功させるには、複数の専門家から提案を受け、比較検討することが重要です。
「メタ住宅展示場の家づくりプラン」のような一括依頼サービスを活用すれば、効率的に情報収集が可能です。複数社から同時に受ける提案では、日除け設備、窓の仕様、通気計画、気密性能、換気システムなど、涼しさに関わる各要素を同条件で比較できます。外付けブラインドを推奨する会社もあれば、深い庇と高性能ガラスの組み合わせを提案する会社もあるでしょう。
土地をお持ちでない場合は、土地探しの段階から支援を受けられます。方位や隣家の影、西日の影響など、涼しい家づくりに重要な要素を考慮した土地選びが可能です。土地の形状や制限を踏まえた間取りプランと合わせて、総合的な提案を受けることができます。補助金の活用についても並走してサポートを受けられます。ZEHや長期優良住宅など、各種制度の適用可否や必要書類、申請スケジュールを事前に確認することで、手戻りのない効率的な家づくりが進められます。
オンラインでの一括依頼なら、忙しい方でも自宅にいながら複数の建築会社から提案を受けられます。
地域の気候特性に精通した地元工務店から、全国展開の大手ハウスメーカーまで、様々な選択肢から自分たちに最適なパートナーを見つけることで、理想の涼しい家づくりが実現します。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)