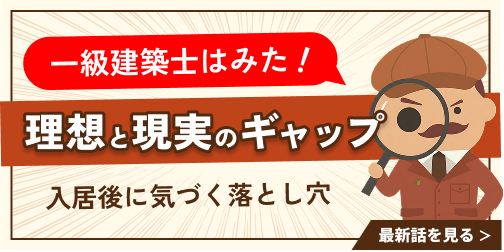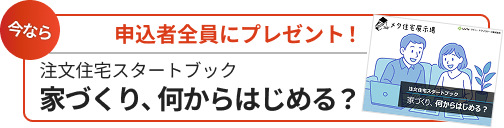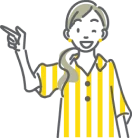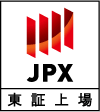日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指し、2030年までにCO2を46%削減する目標を掲げています。この目標達成に向け、多くの分野でCO2排出量削減の取り組みが進んでいます。
住宅業界もその一つです。
住宅業界では、住宅を含む建築物の省エネ性能向上を目的とした「建築物省エネ法」の改正を行い、建築物に対する省エネ性能を社会的要請に応じて段階的に引き上げています。住宅の省エネ性能を高めるために重要なのが「省エネ性能が高い設備の導入」と「断熱性能の向上」です。特に断熱性能は、住宅全体の温熱環境の質を向上させ、健康で快適な生活空間を実現する基盤となります。
断熱性能にはさまざまな指標がありますが、その中でも注目されているのがHEAT20です。
HEAT20を実現することで、1年を通して室内の温度を快適な状態に保ち、ヒートショックの防止や光熱費の大幅削減が可能になります。
しかし、HEAT20は民間の基準であるため、直接的な補助金制度がないなどの課題もあります。ここではHEAT20について、その基準の内容と実現するメリット、建築時の注意点などを詳しく説明していきます。
もくじ
HEAT20(ヒート20)とは?
HEAT20とは、実際に住む人の快適性と健康を第一に考えた、国の省エネ基準を上回る高断熱住宅の性能基準です。
2009年に「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」によって策定されました。HEAT20が策定された背景には、国の省エネ基準が実際の居住快適性や健康を守るには不十分だったことがあります。
国のが定める建築物の省エネ基準では、建物全体の性能を数値で評価されるものの、各部屋の温度差に関する具体的な基準や、結露リスクの詳細な評価など、実生活での快適性に関わる指標は限定的です。そのため、省エネ基準の数値をクリアしていても、実生活では温度差による不快感や健康リスクが残るという問題がありました。
一方、HEAT20は単にエネルギー消費量や外皮性能を満たすだけでなく、室温(NEB)とエネルギー削減率(EB)という「住宅シナリオ」を満たすことを重視しています。
これにより、HEAT20基準を満たした住宅では、家中どこにいても温度差が少なく、冬暖かく夏涼しい、本当に快適で健康的な暮らしを実現できる可能性が高くなります。
断熱性能の高さでG1~3まで分かれる
HEAT20の断熱性能は、G1、G2、G3の3つのグレードに分かれています。数字が大きいほど断熱性能が高く、それぞれに明確な目標が設定されています。
| グレード | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 結露防止・健康確保 | 快適性の向上 | 世界トップレベル |
| 冬の最低室温 (暖房なし) |
おおむね10℃以上 | おおむね13℃以上 | おおむね15℃以上 |
| 省エネ効果※ | 約30~40%削減 | 約50~60%削減 | 約70~80%削減 |
| UA値の例 (東京等6地域) |
0.56以下 | 0.46以下 | 0.26以下 |
| 特徴 |
|
|
|
まずG1グレードは「結露を防いで健康を守る」ことが目的です。
冬場でも暖房を使っていない部屋の温度を10℃以上に保ちます。これにより窓や壁の結露を防ぎ、カビの発生を抑えることができます。従来の住宅では、暖房していない部屋が5℃以下になることもありましたが、G1なら極端な寒さを感じることがなくなります。
G2グレードは「より快適な暮らし」を実現します。暖房なしでも室温を13℃以上に保ち、リビングと廊下、トイレなど家中の温度差を小さくします。部屋を移動するときの「ヒヤッ」とする感覚がなくなり、高齢者に多いヒートショックのリスクも減らせます。
最上位のG3グレードは「世界トップレベルの快適さ」を提供します。暖房なしでも15℃以上を維持でき、真冬でもほぼ暖房を使わずに快適に過ごせます。これはドイツなどヨーロッパの厳しい省エネ基準と同等の性能です。
東京などの地域では、断熱性能を示すUA値(数値が小さいほど高性能)がG1で0.56以下、G2で0.46以下、G3で0.26以下と設定されています。
このように3段階のグレードがあることで、予算や求める快適さに応じて選べるのがHEAT20の特徴です。
ZEH・断熱等級との違い
住宅の断熱性能を表す基準には、HEAT20、ZEH(ゼッチ)、断熱等級の3つがありますが、それぞれ「目指すもの」が違います。
例えば、HEAT20は「住む人の快適性と健康」を第一に考え、冬でも家中が暖かく健康的に暮らせる家を目指しています。一方、ZEHは「エネルギー収支ゼロ」を目標とし、太陽光発電などで使うエネルギーを自給自足する家を実現しようとしています。
そして断熱等級は、国土交通省が定める「外皮の断熱性能の等級付け」に関する住宅性能表示の評価基準です。消費者が客観的な指標で住宅を比較・選択できるよう性能を見える化し、紛争の予防と迅速な解決に資することを目的としています。
運営する団体も異なり、HEAT20は民間の研究会、ZEHは経済産業省・環境省、断熱等級は国土交通省がそれぞれ管理しています。
つまり、3つは「どれが上か」ではなく役割がちがうのです。
- 断熱等級:家の外まわり(壁・窓など)の基本性能をはかる“ものさし”
- HEAT20:家の中がどれだけ暖かく・涼しく感じるかの“目安”
- ZEH:家のエネルギーの出入りをゼロに近づける“目標”
家づくりは、まず断熱等級で土台の性能を確認 → 次にHEAT20で暮らし心地をチェック → 最後にZEHでエネルギー収支や補助の条件を確認、の順で見ると迷いにくいです。どれか1つの数字だけで決めず、同じ条件で比べると失敗しにくくなります。
HEAT20におけるグレードごとの基準と特徴
HEAT20の3つのグレードについて、具体的な数値基準と実現される居住環境の違い、さらに光熱費への影響について詳しく見ていきましょう。
家全体の断熱性能を示すUA値の違い
UA値(外皮平均熱貫流率)は住宅全体の断熱性能を示す重要な指標で、数値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。
HEAT20では全国を8つの地域に区分し、それぞれの気候に応じた目標値を設定しているのが特徴です。これは画一的な基準ではなく、地域の実情に合わせた現実的な目標設定となっているためです。
具体的な数値を見ると、東京や神奈川などの温暖地(地域区分6)では、G1がUA値0.56以下、G2が0.46以下、G3が0.26以下。一方、北海道などの寒冷地(地域区分1・2)では、G1が0.34以下、G2が0.28以下、G3が0.20以下とより厳しい基準が設定されています。
特筆すべきは、関東地域のG3レベル(UA値0.26)が、ドイツやスウェーデンなどヨーロッパの先進的な省エネ基準と同等の水準であることです。これは世界的に見てもトップクラスの断熱性能といえます。
ただし重要なのは、HEAT20の本質がUA値という数値だけにあるのではなく、その性能によって実現される快適な室内環境にあるということです。
グレードによってかわる最低室温と温度のムラ
HEAT20の各グレードが実現する冬期最低室温は、住み心地と健康に直結する最も重要な指標です。
まずG1グレード(最低室温おおむね10℃以上)では、暖房していない部屋でも極端な冷え込みを防ぐことができます。これにより従来の住宅で問題となっていた廊下やトイレの寒さが大幅に改善され、結露の発生も抑制されます。
G2グレード(最低室温おおむね13℃以上)になると、家中の温度差が格段に小さくなります。
リビングから廊下に出た際の「ヒヤッ」とする感覚がなくなり、温度のバリアフリー化が実現。高齢者のヒートショック事故のリスクを大幅に低減できるレベルです。実際、鹿児島県など比較的温暖な地域でも、冬の寒さによるヒートショックが問題となっていますが、G2以上なら安心です。G3グレード(最低室温おおむね15℃以上)では、ほぼ無暖房でも快適に過ごせる環境となります。東京などの地域では、住宅内で15℃未満となる空間が面積比で2%未満という驚異的な性能を実現。まるで魔法瓶の中にいるような、どこにいても快適な温熱環境が得られます。
このように温度のムラが減ることで、結露やカビのリスクが低下し、建物の耐久性向上にもつながるのです。
暖房負荷と光熱費の比較
HEAT20基準の住宅では、従来の省エネ基準住宅と比較して劇的な光熱費削減が可能です。
関東地域における具体的な削減率を見ると、G1で約40%、G2で約55%、G3では約75%もの暖房エネルギー削減が実現できます。これは従来の住宅で月額1万円かかっていた冬の暖房費が、G3レベルでは2,500円程度まで削減できることを意味します。年間で考えると、暖房費だけで5〜10万円以上の節約が可能です。さらに夏の冷房費も含めれば、年間10万円以上の光熱費削減も現実的な数字となります。30年間では300万円以上の節約となり、初期投資の差額を十分に回収できる計算です。
実際、東北地方のある試算では、断熱等級7(G3相当)の住宅は17年目で初期コストの差額を回収できたという報告があります。
エネルギー価格が上昇傾向にある現在、この経済メリットはさらに大きくなることが予想されます。つまり、HEAT20基準の住宅は初期投資こそ必要ですが、長期的には確実に経済的メリットをもたらす賢い選択なのです。
HEAT20のメリット
HEAT20基準を満たす住宅は、初期投資以上の価値を長期的にもたらします。
省エネによる経済的メリットから、健康面での安心、さらに資産価値の維持まで、老後の生活を見据えた住まいづくりに欠かせない5つの大きなメリットを解説します。
①省エネによる光熱費の削減
HEAT20基準の住宅における最大のメリットは、優れた断熱性能による光熱費の大幅削減です。
その理由は、高断熱住宅が外気温の影響を受けにくい「魔法瓶」のような構造になっているからです。夏は外部の熱を遮断し、冬は室内の暖気を逃がさないため、少ないエネルギーで快適な室温を維持できます。具体的には、G3レベルの住宅では従来比で暖房費を4分の1程度まで削減可能です。年間10万円の光熱費削減なら、10年で100万円、30年で300万円以上の節約になります。
さらに全館空調を導入しても、従来の部分暖房と同等以下のエネルギー消費で済むため、家中どこでも快適な温度を保ちながら省エネを実現できます。このように、HEAT20基準の住宅は地球環境への貢献と家計の節約を両立できる、まさに一石二鳥の選択といえるでしょう。
②結露・カビのリスク低減
高断熱住宅では、結露とカビの発生を大幅に抑制でき、家族の健康と建物の耐久性を守ることができます。
室内の壁や窓の表面温度が下がりにくいため、空気中の水蒸気が結露として現れにくくなるためです。HEAT20レベルの住宅では、暖房していない部屋でも一定の室温(G1でおおむね10℃以上、G2でおおむね13℃以上)を保てるため、押入れや浴室の黒カビ発生リスクも小さくなります。実際に、冬場の窓ガラスの結露がほぼゼロになり、毎朝の水拭き作業から解放されます。
また、壁内結露による柱や梁の腐食、シロアリ被害のリスクも低減され、建物の寿命が大幅に延びます。アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖も防げるため、特に小さなお子様がいる家庭には大きなメリットです。結露・カビの問題から解放されることで、健康的で快適な住環境と、建物の資産価値を長期間維持できるのです。
③室温が1年中安定しやすい
HEAT20基準の住宅は、一年を通じて室温が安定し、健康リスクの低減と災害時の安全性を確保できます。その理由は、高い断熱性能により外気温の影響を受けにくく、エアコンを止めた後も室温が急変しないためです。魔法瓶のような保温・保冷効果により、快適な室温を長時間維持できます。
具体的なメリットとして、まずヒートショック防止があります。家中の温度差が小さいため、入浴時や夜間のトイレでの急激な血圧変動を防ぎ、実際に高断熱住宅への転居により居住者の血圧が改善したという調査結果も報告されています。さらに停電時の安全性も重要です。G3レベルの住宅では、真冬に暖房が停止しても室温をおおむね15℃以上に保つことができ、災害時でも家族の健康を守れます。猛暑時のエアコン故障でも急激な室温上昇を防ぎ、熱中症リスクを軽減します。
このように、室温の安定は日常の快適性だけでなく、家族の健康と安全を守る重要な要素なのです。
④住宅の長寿命化・耐久性向上
HEAT20基準の住宅は、建物の寿命を大幅に延ばし、長期的な資産価値を維持できます。
これは高断熱・高気密により結露を防ぎ、構造体の劣化を抑制できるからです。室内外の温度差が小さくなることで、建材の伸縮や歪みも減少し、経年劣化を緩和します。実際のメリットとして、木材の腐朽やサビを防ぎ、シロアリ被害のリスクを低減できます。適切な計画換気により壁内の湿気も排出されやすく、構造躯体を乾燥状態に保てます。
日本の木造住宅の平均建替え周期は約30年といわれていますが、HEAT20基準の住宅は50年以上の使用も十分可能です。建物寿命の延長により、将来の大規模修繕や建替えコストを削減でき、次世代に良質な資産として引き継ぐことができるのです。
⑤資産価値が落ちにくい
HEAT20基準の住宅は、将来にわたって高い資産価値を維持できる可能性が高い住宅です。
その理由は、省エネ性能の高い住宅が中古市場でも高く評価される時代になりつつあるからです。国も住宅の省エネ性能表示を推進しており、断熱性能が明確に示される時代には、高性能住宅の価値がより明確になります。具体的には、G2やG3レベルの住宅は20年後でも高性能住宅として評価され、一般的な住宅より高い査定額が期待できます。
また、光熱費が安い「維持費がかからない家」は購入希望者にとって大きな魅力となります。実際、一部の金融機関では省エネ性能の高い住宅向けに金利優遇ローンを提供しています。つまり、HEAT20基準の住宅への投資は、快適な暮らしを実現するだけでなく、将来の資産価値を守る賢い選択といえるのです。
HEAT20のデメリット
高性能な断熱住宅には多くのメリットがある一方で、建築時に考慮すべき課題もあります。初期コストの増加や施工会社の選定など、HEAT20基準の住宅を建てる際に知っておくべき3つのデメリットと、その対処法について説明します。
①建築コストの高騰
HEAT20基準、特にG2やG3レベルの住宅は、一般的な住宅と比較して建築コストが数十万円から数百万円単位で高くなります。その理由は、高性能な断熱材や窓などの建材が必要となるためです。
G2以上を実現するには、窓は樹脂製フレームにトリプルガラスが必須となり、断熱材も高性能品を厚く充填する必要があります。具体的には、窓はYKK APの「APW430」やLIXILの「エルスターX」といった高性能サッシが必要で、一般的なアルミ樹脂複合ペアガラスサッシより高価です。断熱材も高性能グラスウールの厚充填、外張り断熱の追加、セルロースファイバーや発泡ウレタンなど高性能材料の使用が必要となります。
ただし、長期的な光熱費削減効果を考慮すれば、15〜20年でコスト差を回収でき、それ以降は純粋な経済メリットとなります。初期投資を将来への投資と捉え、ライフサイクルコストで判断することが重要です。
②補助金や補助制度の対象外
HEAT20は民間の基準であるため、HEAT20を満たしたことに対する直接的な国の補助金制度は存在しません。
これはZEHのように国が推進する制度ではなく、民間の研究会による提案であるためです。ZEHなら数十万円から100万円以上の補助金が受けられますが、HEAT20にはそのような制度がありません。
しかし、HEAT20基準を満たす住宅は多くの場合、ZEHや長期優良住宅の基準もクリアできます。G2以上の断熱性能があれば、ZEHに必要な断熱要件は満たしやすくなります。
ただし、ZEH認定を取得するには断熱性能だけでなく、一次エネルギー消費量を基準値から20%以上削減し、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を搭載して正味のエネルギー消費量をゼロにする必要があります。また、自治体によっては断熱等級6以上を対象とした独自の補助制度もあります。
したがって、HEAT20基準の住宅を建てる際は、ZEHや地域の補助制度も併せて検討し、活用できる制度を最大限利用することが賢明です。
③施工できるハウスメーカーが限定される
HEAT20のG2、G3レベルに対応できる住宅会社は限られており、慎重な施工会社選びが必要です。なぜなら、高度な断熱・気密施工技術と緻密な設計計画が必要で、施工精度が低ければ計算上の性能が実現できないからです。隙間なく断熱材を充填し、気密シートを丁寧に貼るなど、熟練の技術が欠かせません。
HEAT20(G3)に対応可能な主なハウスメーカーや工務店は以下の通りです。
| 住宅システムの名称 | 認証日 追加・変更日 | 認証取得者 |
|---|---|---|
| (株)アライ 目指します暖房機の動かない住宅 | 2022.5.26 | 株式会社アライ |
| WELLNEST HOME | 2022.10.21 | 株式会社WELLNEST HOME |
| SANKOの家 G3グレード | 2022.10.21 | 株式会社SANKO |
| サンキハウス G3住宅(屋根断熱) | 2022.12.21 | 静岡三基株式会社 |
| サンキハウス G3住宅(天井断熱) | 2022.12.21 | 静岡三基株式会社 |
| ヤマト住建断熱システム HEAT-G3-Style1 | 2023.3.23 | ヤマト住建株式会社 |
| ロハスな家 G3グレード | 2023.4.26 | 株式会社小林工業 |
| ヴァルマの家 プレミアム | 2023.5.31 | 株式会社スズモク |
| 「WOW基準の家」+G3 | 2023.5.31 | 株式会社WOW Holdings |
| アクリアとネオマでつくるG3の家(屋根断熱) | 2023/7/28 | 旭ファイバーグラス株式会社・旭化成建材株式会社 |
| アクリアとネオマでつくるG3の家(天井断熱) | 2023/7/28 | 旭ファイバーグラス株式会社・旭化成建材株式会社 |
| ラクジュG-Lap | 2023/7/28 | 株式会社ラクジュ |
| S-ZEH | 2023/10/25 | ⼀般社団法⼈⾼性能住宅コンソーシアム |
| アーバンハウス SW2×6 DUALシステム YAHAGI | 2023/10/25 | 株式会社アーバンハウス |
| 中庭の家 G3 | 2023/11/28 | 中庭住宅株式会社 |
| 北洲ハウジング ダブル断熱タイルシステム G3グレード | 2023/12/25 | 株式会社北洲 |
| アクリアとネオマでつくるG3の家(屋根断熱)*追加仕様の承認 | 2024/4/3 | 旭ファイバーグラス株式会社・旭化成建材株式会社 |
| アクリアとネオマでつくるG3の家(天井断熱)*追加仕様の承認 | 2024/4/3 | 旭ファイバーグラス株式会社・旭化成建材株式会社 |
| ケントホームズプレミアムG3 | 2024/6/6 | 株式会社ケントホームズ |
| さいたま家づくりネットワーク「さいたま健康省エネ住宅」G3 | 2024/10/10 | さいたま家づくりネットワーク |
| Fujishima-HEAT20 G3 Type-AT | 2024/12/11 | 株式会社藤島建設 |
| Fujishima-HEAT20 G3 Type-AY | 2024/12/11 | 株式会社藤島建設 |
| grand G3認証仕様 | 2024/12/11 | 株式会社日建ホームズ |
| タカノホーム断熱住宅システムTOPS-G3 | 2025/3/6 | タカノホーム株式会社 |
| 島野工務店 外断熱仕様 S-G3シリーズ | 2025/4/30 | 株式会社島野工務店 |
出典:一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会 住宅システム認証「認証システム一覧」
HEAT20の最新情報や対応可能なハウスメーカーについては、一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会をご確認ください。
施工会社選びのポイントは、G2/G3の施工実績、UA値やC値(気密測定値)の実測・公表、C値1.0㎠/㎡以下(できれば0.5以下)の実現能力です。
しかし、HEAT20対応可能な会社を一社ずつ調べるのは時間と労力がかかります。そこで活用したいのが、複数の建築会社から一括で家づくりプランを取り寄せられるサービスです。住宅展示場を回らなくても、ネットから複数社に家づくりプランを一括請求できるサービスがあります。
このようなサービスを利用することで、HEAT20対応可能な建築会社から土地の提案、間取りプラン、資金計画書を無料で取り寄せることができます。
特に以下のメリットがあります。
- 実際に足を運ばなくても自宅で複数社の提案が受けられる
- 各社のプランを比較検討でき、HEAT20対応の実績や技術力を確認できる
- 資金計画書により、初期コストと長期的なランニングコストを具体的に把握できる
HEAT20基準の高断熱住宅は初期投資が大きくなるため、複数社の提案を比較して、技術力と価格のバランスが最適な会社を選ぶことが重要です。大手ハウスメーカーから地域に特化した工務店まで、さまざまな選択肢から最適な施工会社を見つけることで、理想のHEAT20住宅が実現できるでしょう。
HEAT20の注文住宅を建てる前に「家づくりプラン」でハウスメーカーを比較
HEAT20(G1~G3)に対応するハウスメーカーでも、実際の仕様は多様です。
例えば、目標UA値や窓の等級・ガラス構成、断熱工法(充填/外張り/付加断熱)、熱交換換気の方式と効率、気密の実測値(C値)、全館空調や太陽光・蓄電の有無、保証・メンテ費用の考え方などは、ハウスメーカーごとに差が出ます。だからこそ「比較」が欠かせません。
複数のハウスメーカーを比較するには、メタ住宅展示場の「家づくりプラン」をご活用ください。複数の建築会社にプランを一括で依頼でき、無料で受け取れます。オンラインで土地提案・間取りプラン・資金計画まで揃うので、HEAT20仕様とコストを同一フォーマットで見比べられます。ぜひこの機会にご利用ください。
この記事の編集者
 メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場 編集部
メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)